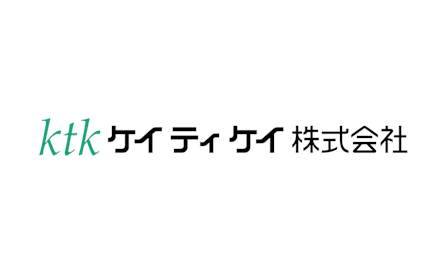
ケ��イティケイ(株)
東証STD、名証メイン 3035
決算:8月20日
20260116
CP&X
【2026年8月期1Q】
【サマリー】
決算概要
当四半期においては、利益率が高い自社製品の拡販やPC販売等の増加により、前年同期比で増収増益を達成。自社製品の拡販においては、重点施策として取り組んできた新規営業活動の成果が現れ始めたことが、大きく貢献。また、リユーストナーの市場再編が進行する中で、当社の製造直販型の安定した供給・品質管理体制と強固な顧客基盤が、優位性を発揮。加えて、IT関連でもWindows11への切り替え需要によるPC販売等が引き続き好調に推移したことで、サプライ事業・ITソリューション事業ともに前年同四半期比で増収増益。
これらの結果、当四半期の売上高は4,715,605千円(前年同期比8.5%増)、営業利益は105,042千円(前年同期比62.5%増)、経常利益は135,336千円(前年同期比44.0%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は83,329千円(前年同期比47.6%増)となった。
セグメント別または事業別の増減要因
(サプライ事業)
重点的に推進してきた新規営業活動が奏功したことで、自社製品の拡販が順調に推移し、特に利益が大きく伸長。これらの結果、売上高は3,541,789千円(前年同期比5.5%増)、セグメント利益は222,605千円(前年同期比26.3%増)となった。
(ITソリューション事業)
Windows11への切り替え需要によりPC販売等が好調に進み、増収増益。これらの結果、売上高は1,173,815千円(前年同期比18.4%増)、セグメント利益は34,518千円(前年同期比26.2%増)となった。
通期見通しと進捗率・達成可能性
進捗率は、売上高24.4% 営業利益22.3%、経常利益24.6%、EBITDA24.4% 親会社株主に帰属する四半期純利益23.8%と、概ね順調に推移。
トピックス
(サプライ事業)
市場再編が進行する中でも、当社のリユーストナー販売本数は増加し、売上・利益に貢献。
(ITソリューション事業)
Windows11への切り替え需要に応じたPC販売が増加し、スキャニングサービス案件も増加。

企業名
上場市場 証券コード
決算日
取材アーカイブ
CP&X
【2025年8月期(通期)】
決算概要
サプライ事業の復調とIT特需により売上・営業利益が伸長
2025年8月期の業績は、売上高18,927百万円(前期比4.5%増)、営業利益426百万円(同11.3%増)、経常利益515百万円(同5.4%増)、当期純利益332百万円(同3.8%減)での着地。主力のリユーストナー等を扱うサプライ事業が、長年の横ばい傾向から脱却し増収増益基調へ転換したことが寄与。ITソリューション事業においても、Windows 11への移行に伴う特需を確実に取り込み、全社業績を牽引。
セグメント別または事業別の増減要因
競合撤退による残存者利益とPC特需の捕捉
サプライ事業は、既存顧客維持に加え新規開拓営業へ注力した成果が発現したほか、リユーストナー事業における「残存者利益」の影響により販売本数が増加。ITソリューション事業は、Windows 11移行に伴うPC入替特需を入り口とし、ネットワークやセキュリティ等の付帯サービス提供へ繋げたことが奏功。加えて、提携先新興企業のSaaSやアプリ(エンゲージメント関連等)のクロスセル販売も伸長。
主要KPIの進捗と変化
トナー販売本数の増加とIT人材採用の改善
サプライ事業における重要指標であるトナー販売本数は、競合環境の変化(撤退)を背景に増加基調で推移。人材戦略においては、新卒採用(年平均4〜5名)の継続に加え、中途採用にて首都圏手当拡充等の給与改定を実施した結果、応募反応が良化。IT領域ではスタートアップ企業との連携強化により、他社製サービスの販売機会数が増加傾向。
季節性・一過性要因の有無と影響
特段の損失要因はないもののPC特需一巡を想定
当期の業績を大きく毀損するような一過性の損失要因は特段見当たらないとの認識。ただし、ITソリューション事業の好調要因となったWindows 11移行に伴うPC入替需要は特需的な側面が強く、今後は需要一巡による伸び悩みのリスクを内包。今後の成長維持には、特需を契機としたストック型サービスや付帯サービスの積み上げが鍵となる構造。
通期見通しと進捗率・達成可能性
前期の延長線上での着実な成長と課題完遂を志向
2026年8月期の業績予想は、基本的に2025年8月期の延長線上と位置づけ、サプライ事業での微増(増収増益)確保とITソリューション事業による成長牽引を目指す方針。前中期経営計画における未完遂の課題に対し、新たなテーマへの移行ではなく「積み残し課題の確実な仕上げ」を重視して取り組む計画。株主還元は配当性向30%を目処とし、前期比1円増配の年間18円(4期連続増配)を予想。
トピックス
障がい福祉事業のM&Aによる業務内製化とコスト削減
2025年7月に障がい福祉事業を行う株式会社じぶんスペースをグループ化し、2026年8月期より連結対象化。同社の売上規模は限定的であるものの、ITスキルを保有する事務局社員や利用者を活用することで、従来外注していた業務の内製化によるコスト削減およびIT事業の人材工数増加といったシナジーを期待。IT関連事業強化に向けたスタートアップ企業との関係深化も継続中。
【2025年8月期(通期)】
Q:成長戦略のポイント(今後の取り組みやトピックス、計画にない新たな戦略的施策等を含む)はなんでしょうか?
A:成長事業と位置付けているITソリューション事業の拡大が主軸となります。具体的な成果として、提携関係にある新興企業が開発したアプリやSaaS系サービス、特にエンゲージメント関連のサービスなどを当社がクロスセルで販売する機会が増加しており、こうした取り組みを継続します。また、人材採用に関しては、新卒採用に加えて中途採用を強化するために首都圏での手当を拡充する給与改定を実施しました。これに対する反応は良好であり、今後は特に首都圏での増員に向けた採用活動を活発化させ、事業成長の基盤を固めていく方針です。
Q:成長戦略のポイントについて、前提条件等での変化とその影響等をご説明ください。
A:主力であるサプライ事業(トナー・文具等)において、長らく続いていた横ばいの状況から増収増益基調へと反転したことが大きな変化です。これは、既存顧客の維持だけでなく新規営業活動に注力した効果が現れたことによるものです。加えて、リユーストナー事業における「残存者利益」として販売本数が増加していることも好調の要因となっています。一方で、ITソリューション事業に関しては、Windows 11への移行に伴うパソコン入れ替え特需が一巡することで、今後は伸び悩む可能性も想定していますが、ネットワークやセキュリティなどの付帯サービス提供につなげることで成長維持を図ります。
Q:通期予想の戦略と施策についてご説明ください。
A:2026年8月期の業績予想については、大枠として2025年8月期の延長線上にあると考えています。基盤ビジネスであるサプライ事業については、現在の好調な状況を維持しつつ微増(増収増益)を確保する計画です。その上で、基本的にはITソリューション事業によって全体としての成長を目指すという構造で業績を予想しています。
Q:受注・競合状況は如何でしょうか?
A:サプライ事業においては、主力のリユーストナー事業で、いわゆる「残存者利益」の一部が出ているものと認識しており、その影響を含めて当社のトナー販売本数が増加している状況にあります。また、これまで十分に対応できていなかった新規開拓営業に注力したことで、予想以上の成果と手応えを感じています。ITソリューション事業では、Windows 11への移行に伴うパソコン特需があり、それを入り口とした関連サービスの受注につながりました。
Q:M&A、業務提携、事業売却などの実施または検討状況と、それに伴う影響についてご説明ください。
A:2025年7月に障がい福祉事業を行う株式会社じぶんスペースをグループに迎え入れ、2026年8月期から連結対象となります。対象会社の売上規模は大きくないため、連結売上・利益への直接的な貢献は限定的ですが、同社の事務局社員や利用者の多くがITスキルを保有している点にシナジーを見出しています。これまで外部に委託していた業務の一部を内製化することで直接的なコスト削減効果が見込めるほか、ITソリューションビジネスに携わる人材の工数増加にもつながるため、ITソリューション事業を伸長させる基盤が整ったと考えています。また、IT関連事業の強化に向けてスタートアップ企業との関係を深めており、新興企業のサービスを当社が販売するクロスセル等の成果が出始めています。
Q:中期事業計画の内容や進捗状況等をご説明ください。
A:基本的には前中期経営計画の延長線上での取り組みを進めていく方針です。前計画において完遂できていない課題や積み残しがあるため、次々と新しい課題へ移行するのではなく、これらの積み残した課題を確実に仕上げていくことを重視しています。したがって、2025年以降に向けた取り組みも、これまでの経営計画の継続と深化であると捉えています。
Q:株主還元の方針をご説明ください。
A:株主還元の方針に変更はなく、配当性向30%を目処としています。進行期については、前期比1円増配の年間18円を予想しており、これで2023年以降4年連続での増配となる見込みです。着実な増配を継続することこそが株主の皆様への最良のメッセージであると考えており、今後もこうした増配傾向を継続していく意思を持っています。
【2025年8月期(通期)】
取材者:初めに、2025年8月期の決算状況をお聞かせいただけますか。
売上高は18,927百万円で前年度比4.5%増、営業利益は426百万円で前年度比11.3%増、経常利益は515百万円で前年度比5.4%増、当期純利益は332百万円で、前年度比3.8%減です。
目標を達成し、好調な決算と拝見しました。増減要因をご説明いただけますか。
回答者:セグメント別にご説明します。サプライ事業、すなわちトナーや文具などの事業と、成長事業であるITソリューション事業の双方が好調でした。サプライ事業は、主力である自社製造のリユーストナーにおいて、新規営業活動の効果が現れ、売上が伸長しました。これまでの横ばい、踊り場の状況から反転した点が、増収増益の要因です。ITソリューション事業は、Windows 11への移行に伴うパソコン特需が要因です。パソコン導入を入り口に、ネットワークやセキュリティなどのサービス提供につなげられた点が、好調の主な理由と考えています。
取材者:第2四半期はITソリューションが好調でしたが、下半期はサプライ事業も伸長したイメージですか。
回答者:その通りです。ITソリューションは、パソコン入れ替え特需の一巡により伸び悩む可能性がありますが、通期決算についても前回お話しした要素と同様です。サプライ事業は長らく横ばいが続いていましたが、新規営業活動の効果が予想以上にあると手応えを感じています。従来そこまでできていなかったという実態があるのですが、既存顧客の維持に重きを置き、新規開拓が滞っていましたが、注力した成果が出ています。また、リユーストナー事業における「残存者利益」も出てきており、その影響を含めてトナーの販売本数が増加している状況です。
取材者:前回、IT関連事業の強化に向けてスタートアップ企業との関係を深めるというお話がありましたが、成果や業績につながるものはございますか。
回答者:根本的な成果はこれからですが、分かりやすい成果として、新興企業が開発したアプリやSaaS系サービスを、当社がクロスセルで販売するケースが増えています。具体的には、エンゲージメント関連のサービスなどで、ご購入いただく機会が増えていると実感しています。
取材者:7月に株式会社じぶんスペースをグループインしたとのニュースがありましたが、影響はいかがですか。
回答者:前期、2025年8月期への影響はありません。進行期である2026年8月期から連結対象となります。事業内容は障がい福祉事業であり、現状の売上規模は大きくないため、M&Aによる売上・利益への貢献は限定的です。ただし、じぶんスペースの事務局の社員や利用者の多くがITスキルを保有しています。これまで内部で対応できず外注していた業務の一部を内製化することで、直接的なコスト削減効果が期待できます。また、ITソリューションビジネスに携わる人材の工数増加にもつながるため、ITソリューション事業を伸長させる基盤が整ってきたと考えています。
取材者:採用数の推移はいかがですか。
回答者:順調とは言えませんが、新卒と中途の両面で進めています。新卒採用はグループ全体で毎年コンスタントに平均4〜5名を採用しています。中途採用は難しい状況でしたが、今期(進行期)に入り、首都圏の手当を拡充する給与改定を行いました。その結果、反応が良くなっており、今後は特に首都圏での増員に向けて採用活動を活発化したいと考えています。
取材者:今期の業績に影響を与えたような一過性の要因はございますか。
回答者:特に見当たりません。
取材者:2026年8月期の業績予想について、見通しはいかがですか。
回答者:大枠として、2025年8月期の延長線上で考えています。基盤ビジネスであるサプライ事業は微増(増収増益)を維持し、基本的にはITソリューション事業で成長を目指す予測です。
取材者:今期、新たに取り組む重要施策はございますか。
回答者:基本的には前中期経営計画の延長線上であり、積み残した課題への取り組みとなります。課題を完遂できていない部分があるため、新しい課題へ次々と移行するのではなく、積み残しを確実に仕上げていく認識です。
取材者:2025年中期経営計画に向けての取り組みと捉えてよろしいですか。
回答者:その通りです。
取材者:株主還元の方針に変更はございますか。
回答者:変更はありません。配当性向30%を目処とし、今期(進行期)は前期比1円増配の年間18円を予想しています。2023年以降、4年連続で1円ずつの増配となりますが、着実な増配を継続することが、株主の皆様への最良のメッセージになると考えています。今後もこうした傾向を継続したいという意思を表明しています。
取材者:その他、足元の状況についてトピックスやニュースリリースはございますか。
回答者:特にありません。
専務取締役管理本部長兼グループ戦略本部長
葛西 裕之 様

企業名
上場市場 証券コード
決算日
取材アーカイブ
CP&X
決算概要2025年8月期第2四半期の売上高は91億6,400万円と前年同期比5.9%の増加、営業利益は1億6,600万円と前年同期比12.7%の増加、経常利益は2億1,800万円と前年同期比4.7%の増加、中間純利益は1億3,700万円と前年同期比13.7%の減少となった。中間純利益の減少は、当中間期において政策保有株式の売却が少額に留まったことが要因である。全体として、ITソリューション分野の伸びが業績を牽引している状況である。
セグメント別または事業別の増減要因
売上高は主にITソリューションセグメントが伸長している。営業利益はITソリューションセグメントが前年同期比131%と大幅に増加した一方、基盤事業であるサプライセグメントは同97%であった。ITソリューション事業はパソコン関連を含め、Windows関連が好調に推移しており、ビジネスにとって良い状況である。
主要KPIの進捗と変化
当社は、直接的なKPIとして特定の数値を挙げてはいないものの、ITに関連する事業機会を捉えるための重要な取り組みとして、スタートアップ企業との交流を積極的に行っている。これは、自社の感覚をアップデートし、世の中に増えている実用的なテクノロジーをお客様への提供や社内展開に繋げる可能性を模索するためである。
季節性・一過性要因の有無と影響
今期の業績に影響を与えるような季節性または一過性の大きな要因はない。当社のビジネスは、個別の大型案件よりも、小口取引を継続的に積み上げていく事業構造であるため、一過性の要因が出にくい特性を持つ。
通期見通しと進捗率・達成可能性
通期見通しに対する進捗率は、中間期まではおおむね予算の範疇であると認識している。中期経営計画の達成はITソリューション事業の成長にかかっており、IT人材の確保やIT関連への取り組みを通じて、非連続とまではいかないまでも着実に成長を目指していく方針である。
トピックス
トピックスとしては、コスト削減ニーズの高まりを背景に、リユース・リサイクルトナーの優位性が再評価されている点がある。当社のリユース品は純正品の約3分の1の価格で提供可能であり、他社製品と比較してもさらに3割程度安価に提供できるという価格競争力を持つ。これは自社工場で製造していることに起因する。
加えて、S.P.P.(サステナブルパートナープログラム)を展開している。これは、トナーカートリッジにQRコードを付与し、工場出荷時、回収時、顧客による装着時にQRコードを読み取ることで完全なトレーサビリティを確保するものである。これにより、プラスチック廃棄量の削減やCO2排出量の削減といった環境貢献度を数値化し、環境貢献レポートとして顧客企業に提供することが可能である。このプログラムは、コスト削減と環境貢献の両面から顧客に価値を提案するものであり、経営層への訴求力も高い注目点である。
Q:成長戦略のポイント(今後の取り組みやトピックス、計画にない新たな戦略的施策等を含む)はなんでしょうか?
A:当社はITソリューション分野の成長に注力しており、特にWindows環境を含めたパソコン関連のビジネスが好調に推移しています。また、環境に配慮したリユース・リサイクルトナーの事業も重要な柱と位置づけています。特に、純正品の3分の1程度の価格で提供できるリユース品は、コスト削減を求める製造業などの企業にとって大きなメリットとなっており、環境負荷低減にも貢献できる点を強化して提案していく方針です。
さらに、S.P.P.(サステナブルパートナープログラム)という独自の取り組みを推進しています。これは、使用済みトナーカートリッジにQRコードを付けて管理することで、回収からリユースまでのトレーサビリティを確保し、顧客がどれだけプラスチック廃棄量やCO2排出量を削減できたかを数値で可視化してレポートするものです。これにより、現場の担当者から経営層まで、企業の様々な階層に対して環境貢献とコスト削減の両面で価値を訴求し、プログラムへの参加を促しています。
Q:M&A、業務提携などの実施または検討状況と、それに伴う影響についてご説明ください。
A:具体的なM&Aや業務提携の案件は現時点ではありませんが、IT分野、特に中小企業や小規模事業者が受け入れやすい「泥臭いIT」と表現されるような、入り口となる技術や人材を持つ企業との提携やM&Aを検討していきたいと考えています。これは、当社のビジネスモデルが、個別の大きな案件よりも、きめ細かいサービスを継続的に提供することで成り立っているため、一過性の要因に左右されない事業基盤の強化を目指すものです。
Q:中期経営計画の内容や進捗状況等をご説明ください。
A:現段階では、今回の業績開示の通り、予算組通りに進捗しており、新しい中期経営計画の1年目としては順調に進んでいると認識しています。中期経営計画の達成は、ITソリューション分野がどれだけ成長できるかにかかっています。当社は、M&Aなども含めてIT人材の確保やIT関連への投資を積極的に行い、「非連続の成長」とまではいかないまでも、着実にITソリューション事業を伸ばしていく方針です。8月20日の決算をしっかり達成し、次期に向けてこれらの取り組みを本格化させていく考えです。
Q:株主還元の方針をご説明ください。
A:株主還元については、配当性向30%までを着実に目指すという方針に変わりはございません。これまでも継続的に増配を実施しており、来期以降のことについては現時点では明確な言及は控えますが、30%という目標を掲げている以上、それに向かって着実に実行していく方針です。
また、当社の株主の約97%が個人投資家であるため、配当だけでなく株主優待を望まれる声も多くございます 。そのため、優待制度をより利用しやすいように、昨年度から単元株数を引き下げるなどの変更を行いました。配当の増額と並行して株主優待の充実も図ることが、当社の企業規模において重要な株主還元策であると考えております。
取材者:まず初めに、2025年8月期の第2四半期決算についてお伺いいたします。売上高は91億6,400万円で前年同期比5.9%増加、営業利益は1億6,600万円で前年同期比12.7%増加、経常利益は2億1,800万円で前年同期比4.7%増加、親会社株主に帰属する中間純利益は1億3,700万円で前年同期比13.7%減少とのことですが、かなり好調に業績が推移しているように見受けられます。これについての業績増減要因をご説明いただけますか?
回答者:好調という認識はございません。ITソリューションは一部伸びており、パソコン関連を含め、Windowsの分野も弊社のビジネスにとっては良い状況にあります。売上は主にITセグメントが伸びています。決算資料にも記載しましたが、セグメント別の営業利益ではITソリューションが131%と伸長している反面、基盤であるサプライ事業は97%です。経常利益に関しては、自社サイト「YORIDORI」の開発に伴う減価償却費や、人件費の増加が影響しています。一部IT人材への先行投資も含め、これらの費用が営業利益段階でも関連してきています。また、借入金は少ない方ですが、金利なども少しずつ影響してきています。純利益に関しては、投資有価証券の売却益がありましたが、これは元々織り込み済みです。
取材者:そうしますと、中間予想に対する進捗率はいかがですか?
回答者:数字に関しては、本来であればもっと上を目指したいという気持ちはありますが、第3四半期に割と大きな数字を抱えていることも事実です。中間期までは、予算比に関しても一部営業利益は耐えきれていませんが、概ね想定の範囲内だと考えております。
取材者:その他、今期のここまでの業績に関して、季節的要因や一過性の要因はございましたか?
回答者:一過性の要因は特にございません。
取材者:それは会社全体として見ても、一過性の要因が出にくいということですか?
回答者:良い意味で大きな案件は欲しいところではありますが、弊社のビジネスは細かいものを継続的にご購入いただく商売が多いです。逆に一時的な要因が出ると反動も来てしまうため、現状で妥当だと考えております。
取材者:先ほどIT人材のお話が出ましたが、前期と比較して人材採用数の推移はいかがですか?
回答者:IT人材はもっと採用したいのですが、なかなか確保できていません。ITセグメントに配属された若手はおりますが、IT人材にまではまだ育っていません。
取材者:そこの育成の部分はこれからですね。
回答者:はい。
取材者:IT人材をより採用していくために、何か行われている施策や方針はございますか?
回答者:具体的な話ではありませんが、M&Aなどを通じて会社全体で人材を確保したいという思いはあります。しかし、なかなか良い話はありません。
取材者:中期経営計画に対する進捗度合いはいかがですか?
回答者:現段階では、今回の通期に関しては、予算通りに推移していると考えておりますので、新しい中期経営計画の1年目は、まず達成できるのではないかと思っております。中期経営計画の達成は、ITソリューションが着実に成長するかにかかっています。大きな意味ではありませんが、非連続の成長とまではいかないまでも、人材確保やIT関連への投資などを積極的に行い、伸ばしていきたいと考えております。弊社は8月20日決算ですので、それをきちんと達成した上で、次期にはそういった取り組みを色々行っていきたいと考えております。
取材者:M&Aなどに関して、業務提携も含め、実施のご予定や検討状況、あとは方針についてございましたら、答えられる範囲で教えていただけますか?
回答者:具体的なことはございませんが、ITおよびITを冠するようなことについては取り組んでいきたいと考えております。もう少し話をすると、我々がターゲットとしている中小企業や小規模事業者は、最新のITを提案してもすぐに受け入れてもらえるわけではありません。もう少し実用的なITというか、企業の生産性を向上させるための入口は他にもあると考えております。はっきり言うと、企業にとってはIT投資なのですが、少し遅れて導入されるような分野もあります。そういったところに、リーチすることが出来る技術や人材を持った企業に、ぜひ仲間になってもらいたいと考えております。
取材者:そうすると、かなり幅広い視点から業務提携を含めて検討されているイメージですか?
回答者:その通りです。
取材者:恐れ入ります。その他、貴社にとって主要なKPIはございますか?
回答者:KPIというわけではないのですが、ITに関連して、なるべくスタートアップの方々には会うようにしています。弊社とは全く無関係だろうという人も含めてです。そういった方々の空気を吸いたいという思いがあります。それが直接繋がることはないかもしれませんが、まずはそういったことを踏まえて、我々の感覚をアップデートしていかなければならないと考えております。ITに限らず、テクノロジーというと大げさですが、最先端の話は到底分かりませんが、世の中には実用的なものが増えてきています。そういったものを見て、お客様への提供なのか社内への展開なのかは分かりませんが、それは必要だと感じております。
取材者:そうすると、そういったことがうまく繋がっていくと、中期経営計画のその先も含めて、何か大きなことができそうですね。
回答者:アンテナを張るというか、そういったところは数値化しにくい面もありますが、逆にチャンスが広がったように感じています。
取材者:株主還元の方針について教えていただけますか?
回答者:配当性向は30%まで着実にという方針で、これまでも増配を続けてきておりますので、来期以降のことは現時点ではお話しできませんが、30%という目標を掲げている以上、それに向かって着実に実行していくという方針に変わりはございません。また、弊社の株主のほぼ97%が個人投資家ですので、還元策としては株主優待を望まれる方も多いです。優待制度をより利用しやすいように、昨年度から単元株数を引き下げるなど変更しております。配当を上げつつ優待を充実させることも、弊社の企業規模においては考えていることです。
取材者:承知いたしました。最後に、足元の状況につきまして、トピックスやニュースリリースがございましたら教えていただけますか?
回答者:ニュースというわけではありませんが、いわゆるトランプ関税の影響で、企業の特に製造業はコスト削減をさらに強化しようという動きが強まっています。私どものリユース、リサイクル製品は環境に優しいだけでなく、コスト削減も実現できます。一般的に環境に良いものは価格が高いというイメージがありますが、そうではありません。例えば、純正品トナーとリユース品のトナーでは、価格が約3分の1になります。例えばアスクル様に掲載されている価格よりも、さらに3割ほど安く提供できるのです。弊社は自社工場で製造しておりますので、それが可能です。環境に配慮しつつコスト削減を求める企業に対して、再度提案を強化していきたいと考えております。これは弊社の強みとなる反面、きちんと推進していきたいと考えております。
取材者:確かにそれは、他社との差別化、価格も含めて、かなり期待できそうですね。
回答者:例えばアスクル様に掲載されている商品をアスクル様よりも3割安く提供できる会社は他にあまりないと思います。
取材者:それは今後かなり大きなトピックスになりそうですね。その他何かトピックスはございますか?
回答者:あとは、ホームページでも展開しておりますが、弊社の「SPP(サステナブルパートナープログラム)」についてです。トナーの本体ではなく、箱にQRコードがついています。リユースは使用済みカートリッジをどうするかが重要になります。企業では、トナーの箱に入ったものが在庫として保管されていることが多いです。しかし、実際に箱を開けて、黒いプラスチック製のトナーカートリッジを見るのは、トナー交換時以外にはあまりないと思います。使い終わったものをどうしているかというと、購入時に返却しているという認識はあるものの、きちんと返却されているかまでは把握できていないのが現状だと思います。私どもが企業の経営層や責任者の方とお会いする際には、あえてトナーの本体を持っていくようにしています。箱を開けて、トナーを手に取っていただくと、その重さやプラスチックの感触を感じていただけます。この重たいプラスチックのものをQRコードで管理し、確実に回収し、きちんとリユースして再利用するのだと説明する際、提案書だけを見せるのと、実際に持ってもらうのとでは、伝わり方が違うと考えております。
弊社工場から出荷する際にこのQRコードを読み込み、工場に返却される際も読み込みます。お客様の方でもトナー交換時にQRコードを読み込んでいただくことで、完全なトレーサビリティが確保できます。これにより、使う側の責任も含めて、使用済みのものを確実に返却し、それが再び戻ってくるというサーキュラーエコノミーの概念をお客様と弊社双方で納得できる形で実現します。このサステナブルなプログラムにぜひご参加いただきたいと考えており、当然、お値段も優遇させていただきます。
取材者:今まで見えていなかった部分が可視化されるようなイメージでしょうか?
回答者:はい。価格も安くなるだけでなく、このプラスチックを例えば5回使用することで、5回分の新しいプラスチックを製造する必要がなくなります。これにより、プラスチックの使用量を削減できるのです。その結果を基に、CO2排出量をこれだけ抑えられたという、プラスチック廃棄量の削減とCO2の削減も数値化できます。現場の方にはスキャンしていただくことでポイントが貯まり、ちょっとしたお菓子を差し上げるような仕組みも考えております。課長さんクラスの方には、自動発注も可能で、非常に便利だとお伝えしています。年に1~2回、経営層にはこれだけのCO2削減量を達成したという環境貢献レポートを提出できます。そういった形でプログラムをきちんとご提案していくことを考えております。
取材者:どこの層にも何か刺さるような仕組みになっているのですね。本当にその環境のレポートは経営層にかなり刺さりそうなものですね。
回答者:会社の中で、CO2削減を数値化できるものはあまりありません。正直、1本当たりの削減量は小さいですが、小さくてもプロジェクトとして可視化でき、数値化できるということが重要だと考えております。
代表取締役社長 青山 英生様

企業名
上場市場 証券コード
決算日
取材アーカイブ
ビジネスモデルや事業内容
ケイティケイは、リサイクルトナーの製造販売を基盤とするサプライ事業と、中小企業向けのITソリューション事業を展開しています。ペーパーレス化の流れに対応するため、複合機などお客様のニーズに合わせたITソリューションの提供に力を入れている。また、近年はECサイト「YORIDORI(ヨリドリ)」を立ち上げ、デジタルマーケティングにも注力。これは、グループ会社のイコリスの知見を活かしたもので、売上増加にも貢献しつつある。さらに、既存顧客の囲い込みとリサイクルトナーカートリッジのトレーサビリティ強化を目的としたサステナブルパートナープログラムを導入。これは、トナーカートリッジにQRコードを貼ることで、回収と発注を効率化する仕組みである。
創業の経緯と転機となった出来事
創業は1971年で、当初は特殊紙の製造販売を行っていた。その後、レーザープリンターの普及に伴い、トナーのリサイクル事業を開始し、現在に至る。
特徴や強み
ケイティケイはリサイクルトナーの製造メーカーであり、製造直販を行っているという強みを持つ。 これは、リサイクルトナー業界では数少ないビジネスモデルであり、顧客のニーズに合わせた柔軟な対応を可能にしている。 また、グループ会社である青雲クラウンとのシナジー効果により、文具の販売においても幅広い商品ラインナップを提供できることが強みとなっている。
成長戦略
ケイティケイは、デジタルマーケティングを強化することで、ECサイト「YORIDORI(ヨリドリ)」の売上増加を図っている。 また、サステナブルパートナープログラムを導入し、既存顧客の囲い込みとリサイクルトナーカートリッジのトレーサビリティ強化を推進している。 さらに、M&A戦略として、サプライ事業では事業承継を目的とした小規模なM&Aを、ITソリューション事業ではEC事業やデジタル分野でのM&Aを検討している。
Q:事業内容やビジネスモデル、特徴や強みなどをご説明ください。
A:当社の基盤事業はサプライ事業です。 特徴としては、自社でリサイクルトナーを製造しているメーカーであるという点が挙げられます。 オフィスに必要なものとしてリサイクルトナーを販売する中で、紙や文具、オフィスの家具など、事務所で必要なものは一式販売しており、自社製品とともに仕入れ商品も販売しています。 自社製品は粗利益率が高く、それを基幹商品としてサプライ事業を展開しています。 これが創業以来の基本的なビジネスモデルです。
グループ全体で1万数千社のお客様とトナーを中心に取引をしています。 しかし、ペーパーレス化の流れの中で、お客様のニーズが変わってきました。 かつてはプリンター専用機が各社にありましたが、近年では複合機に集約されるケースが増えています。 なお、当社が販売しているリサイクルトナーはプリンター専用機のためのものです。 複合機はメーカーが純正トナーをカウンター料金制度で提供しているため、当社のリサイクルトナーを販売する余地はありません。
プリンター専用機から複合機への集約など、デジタル化やペーパーレス化の流れの中で需要が変わってきており、それに対応するのがITソリューション事業です。 お客様の中には、「プリンターはいらないけど複合機の買い替えをしたい」という方もいます。 また、パソコンやセキュリティなど、複合機に付随する様々なニーズにも対応しています。
基本的には顧客基盤は共通で、お客様のサプライとITソリューションの両方を契約いただいているケースも多いです。 ITソリューション事業のお客様は中小企業が中心で、従業員50人以下の企業が多いです。 情報システム部門を自社で抱えているような大企業は、お客様にはなりにくいです。 中小企業の情報システム部門の代行や、情報システム担当者を支援するような形でサービスを提供しています。 複合機を起点に、様々な提案や支援をしています。
Q:複合機、プリンター専用機から複合機に変えられるような提案も行っているのでしょうか?
A:プリンター用のリサイクルトナーが当社にとって主力の商品ですので、基本的にはそれを守るというスタンスです。 しかし、例えば「プリンターはいらないから複合機に統合したい」というお客様に対しては複合機の提案も行えるように、全方位の対応をしています。
Q:サプライ事業の中で新たに立ち上げたECサイトについて詳しくご説明いただけますでしょうか?
A:元々「はっするネット」というECサイトを持っていたのですが、これは受発注システムのようなものでした。 Google検索などで外部からお客様が流入してくるようなオープンサイトではなく、既存のお客様にFAXで注文するよりも便利にご利用いただくためのサイトでした。
それを昨年「YORIDORI(ヨリドリ)」というECサイトに一新しました。 これはオープンサイトになっており、外部からの集客もできるようになりました。 既存のお客様のユーザビリティ向上も図り、外部のお客様と既存のお客様の両方から購買を促進することで、客単価の向上を目指しています。
また、「YORIDORI(ヨリドリ)」はデジタルマーケティングのプラットフォームとしても活用しています。 サイトでは様々な商品の紹介だけでなく、ITソリューションに誘導するような記事なども掲載しています。
Q:デジタルマーケティングを主導できるようになったのは、グループ化したイコリスの影響でしょうか?
A:はい、そうです。 元々デジタルマーケティングを強化していこうという方向性があった中で、M&Aの話があり、現在はイコリスを中核にケイティケイにもデジタルマーケティングの部署を設け、昨年8月からWebマーケティングを強化しています。
Q:売上高増加要因としてデジタルマーケティングの伸長がありましたが、現状はイコリスの知見が社内に活かされているということでしょうか?
A:現状、実際に売上利益に直結しているのはイコリスです。 決算説明資料などでもITソリューションの中でイコリスのサプリメントや化粧品販売の話に触れておりますが、現時点ではそちらの貢献が大きいです。
外部からの集客など、イコリスの知見を生かして「YORIDORI(ヨリドリ)」を運営しており、サプライ事業の売上にも貢献しつつあります。
Q:サプライ事業で新規営業活動に対する取り組みについて教えていただけますでしょうか?
A:これはシンプルに言って、コロナ禍で対面型の営業活動が停滞したため、アフターコロナで改めて営業を強化しているということです。
特に東京では、新規の営業活動が難しくなっていました。 当社のリサイクルトナーのメインのお客様は、都心のオフィスだけでなく、製造業、病院、介護、物流などの業界にも多くいます。 これらの業界のお客様に対しても、コロナ禍で営業活動が制限されていました。 病院などは、なかなか電話やメールでは対応できず、実際に行かないと話ができないところが多いのが現実です。
Q:サプライ事業に関しまして、サステナブルパートナープログラムについてご説明いただけますでしょうか?
A:これは端的に言うと、既存のお客様の囲い込み戦略です。 新規顧客獲得も重要ですが、既存顧客の囲い込みも重要です。 また、リサイクル業者としての責任を果たすという側面もあります。 リサイクルは、トナーカートリッジを回収し、再生して販売するというサイクルを回さなければいけません。 しかし、現実には販売したトナーカートリッジを回収できないケースも多いのです。
他の業者に回収されてしまったり、逆に当社が回収する中に売ってないものが含まれていたりするなど、様々な問題があります。 そこで、リサイクルカートリッジのトレーサビリティを強化するために、このサステナブルパートナープログラムを導入しました。
具体的には、トナーカートリッジにQRコードを貼っています。 お客様がトナーを交換する際に、新しいトナーのQRコードを読み取ってもらうことで、古いトナーが返ってくるということがわかるようになります。 そして、それを回収に伺います。 お客様のニーズによっては、自動的に発注も行えます。
お客様にとっては、発注や在庫管理の手間が省けます。 当社にとっては、QRコードを読み取っていただくことで、回収と同時に次のトナーも自動的に発注いただけることになります。
Q:IoT的な側面があるのでしょうか?
A:はい。 リサイクルトナーの会社は、ほとんどが販売店を介したビジネスを行っています。 当社は数少ない製造直販です。 ですので、QRコードで回収や発注ができる仕組みを作れるというメリットがあります。 この辺を今後推進していきたいと考えています。
Q:貴社はおそらくM&Aなどの戦略もあるかと思いますが、M&Aの戦略として何か、こういう企業をターゲットにしているというのはございますか?
A:まず、全方位で情報を集めています。 サプライ事業においては、例えば同業の文具販売店などで、社長が高齢になり事業承継できず、どこかに事業を譲渡したいというケースが増えています。 そのようなケースでは、M&Aというよりも、お客様を引き継ぐというような形になります。 少なくとも仲介業者は入らないような、リリースなども出さないM&Aです。
ITソリューション分野では、例えばイコリスのEC事業をどのように広げていくかということを検討しています。 ECでBtoCで売りたいけれど、ノウハウがないという会社も多いので、イコリスの知見を活かして何かできないかと考えています。 また、全く予想外のデジタル分野のビジネスを持ち込んでくれる方も多く、そのような案件も検討しています。
Q:最後に、貴社の創業の経緯や創業時の思いについてお伺いできますでしょうか?
A:創業は1971年で、加藤という者が創業した会社です。 当時は「カトー特殊計紙」という社名で、特殊な紙を製造販売していました。 この頭文字がKTKという社名の由来です。
その後、Windows95が登場した頃にレーザープリンターが普及し始め、レーザープリンター用トナーのリサイクルビジネスを始めました。 その前は、リサイクルリボンを製造していました。 これは、銀行のATMで通帳記入する際などに使用されるリボンです。 リボンのリサイクルから始まり、今ではインクなどもリサイクルしています。
ケイティケイ単体で2006年にJASDAQに上場しました。 その後、文具卸売業の青雲クラウンと株式交換という形で一緒になり、青雲クラウンのオーナー社長である青山がケイティケイの経営も見るようになりました。
Q:ECサイトで文具を幅広く販売できるようになったのは、青雲クラウンの影響もあるのでしょうか?
A:はい、そうです。 青雲クラウンは歴史のある文具問屋で、商品ラインナップが豊富です。 KTKはトナーに特化していたので、文具に関しては青雲クラウンの力を借りることができました。 両社にとって大きなシナジー効果がありました。
取材者: 事業内容やビジネスモデル、特徴や強みなどをご説明ください。
回答者: 当社の基盤事業はサプライ事業です。特徴としては、自社でリサイクルトナーを製造しているメーカーであるという点が挙げられます。オフィスに必要なものとしてリサイクルトナーを販売する中で、紙や文具、オフィスの家具など、事務所で必要なものは一式販売しており、自社製品とともに仕入れ商品も販売しています。自社製品は粗利益率が高く、それを基幹商品としてサプライ事業を展開しています。これが創業以来の基本的なビジネスモデルです。
グループ全体で1万数千社のお客様がいらっしゃいまして、トナーを中心に取引をしています。しかし、ペーパーレス化の流れの中で、お客様のニーズが変わってきました。かつてはプリンター専用機が各社にありましたが、近年では複合機に集約されるケースが増えています。ちなみに、当社が販売しているリサイクルトナーはプリンター専用機のためのものです。複合機はメーカーが純正トナーをカウンター料金制度で提供しているため、当社のリサイクルトナーを販売する余地はありません。
プリンター専用機から複合機への集約など、デジタル化やペーパーレス化の流れの中で需要が変わってきており、それに対応するのがITソリューション事業です。お客様の中には、「プリンターはいらないけど複合機の買い替えをしたい」という方もいらっしゃいます。また、パソコンやセキュリティなど、複合機に付随する様々なニーズにも対応しています。
基本的には顧客基盤は共通で、お客様のサプライとITソリューションの両方を契約いただいているケースも多いです。ITソリューション事業のお客様は中小企業が中心で、従業員50人以下の企業が多いです。情報システム部門を自社で抱えていらっしゃるような大企業は、お客様にはなりにくいです。中小企業の情報システム部門の代行や、情報システム担当者を支援するような形でサービスを提供しています。複合機を起点に、様々な提案やお手伝いをしています。
取材者: なるほど。複合機、プリンター専用機から複合機に変えられるような提案などもされるということでしょうか?
回答者:プリンター用のリサイクルトナーが当社にとって主力の商品ですので、基本的にはそれを守るというスタンスです。しかし、例えば「プリンターはいらないから複合機に統合したい」というお客様に対しては複合機の提案も行えるように、全方位の対応をしています。
取材者:サプライ事業の中で新たに立ち上げたECサイトについて詳しくご説明いただけますでしょうか?
回答者: はい。元々「はっするネット」というECサイトを持っていたのですが、これは受発注システムのようなものでした。Google検索などで外部からお客様が流入してくるようなオープンサイトではなく、既存のお客様にFAXで注文するよりも便利にご利用いただくためのサイトでした。
それを昨年「YORIDORI(ヨリドリ)」というECサイトに一新しました。これはオープンサイトになっており、外部からの集客もできるようになりました。既存のお客様のユーザビリティ向上も図り、外部のお客様と既存のお客様の両方から購買を促進することで、客単価の向上を目指しています。
また、「YORIDORI(ヨリドリ)」はデジタルマーケティングのプラットフォームとしても活用しています。サイトでは様々な商品の紹介だけでなく、ITソリューションに誘導するような記事なども掲載しています。
取材者: デジタルマーケティングを主導できるようになったのは、グループ化したイコリスの影響でしょうか?
回答者: はい、そうです。元々デジタルマーケティングを強化していこうという方向性があった中で、M&Aの話があり、現在はイコリスを中核にケイティケイにもデジタルマーケティングの部署を設け、昨年8月からWebマーケティングを強化しています。
取材者: なるほど。売上高増加要因としてデジタルマーケティングの伸長がありましたが、現状はイコリスの知見を社内に活かして、うまくデジタルマーケティングを回しているということでしょうか?
回答者: 現状、実際に売上利益に直結しているのはイコリスです。決算説明資料などでもITソリューションの中でイコリスのサプリメントや化粧品販売の話に触れておりますが、現時点ではそちらの貢献が大きいです。
外部からの集客など、イコリスの知見を生かして「YORIDORI(ヨリドリ)」を運営しており、サプライ事業の売上にも貢献しつつあります。
取材者:売上増加要因のところで、サプライ事業で新規営業活動に対する取り組みという記載があったかと思いますが、これについてどのような政策や取り組みを行われているか教えていただけますでしょうか?
回答者: はい。これはシンプルに言って、コロナ禍で対面型の営業活動が停滞したため、アフターコロナで改めて営業を強化しているということです。
特に東京では、新規の営業活動が難しくなっていました。当社のリサイクルトナーのメインのお客様は、都心のオフィスだけでなく、製造業、病院、介護、物流などの業界にも多くいらっしゃいます。これらの業界のお客様に対しても、コロナ禍で営業活動が制限されていました。病院などは、なかなか電話やメールでは対応できず、実際に行かないと話ができないところが多いのが現実です。
取材者:サプライ事業に関しまして、サステナブルパートナープログラムについてご説明いただけますでしょうか?
回答者: はい。これは端的に言うと、既存のお客様の囲い込み戦略です。新規顧客獲得も重要ですが、既存顧客の囲い込みも重要です。また、リサイクル業者としての責任を果たすという側面もあります。リサイクルは、トナーカートリッジを回収し、再生して販売するというサイクルを回さなければいけません。しかし、現実には販売したトナーカートリッジを回収できないケースも多いのです。
他の業者に回収されてしまったり、逆に当社が回収する中に売ってないものが含まれていたりするなど、様々な問題があります。そこで、リサイクルカートリッジのトレーサビリティを強化するために、このサステナブルパートナープログラムを導入しました。
具体的には、トナーカートリッジにQRコードを貼っています。お客様がトナーを交換する際に、新しいトナーのQRコードを読み取ってもらうことで、古いトナーが返ってくるということがわかるようになります。そして、それを回収に伺います。お客様のニーズによっては、自動的に発注も行えます。
お客様にとっては、発注や在庫管理の手間が省けます。当社にとっては、QRコードを読み取っていただくことで、回収と同時に次のトナーも自動的に発注いただけることになります。
取材者: なるほど。IoT的な側面があるのですね。
回答者: はい。リサイクルトナーの会社は、ほとんどが販売店を介したビジネスを行っています。当社は数少ない製造直販です。ですので、QRコードで回収や発注ができる仕組みを作れるというメリットがあります。この辺を今後推進していきたいと考えています。
取材者: 確かに直販でなければできないことになりますね。
回答者: はい。
取材者: 貴社はおそらくM&Aなどの戦略もあるかと思いますが、M&Aの戦略として何か、こういう企業をターゲットにしているというのはございますか?
回答者: そうですね。まず、全方位で情報を集めています。サプライ事業においては、例えば同業の文具販売店などで、社長が高齢になり事業承継できず、どこかに事業を譲渡したいというケースが増えています。そのようなケースでは、M&Aというよりも、お客様を引き継ぐというような形になります。少なくとも仲介業者は入らないような、リリースなども出さないM&Aです。
ITソリューション分野では、例えばイコリスのEC事業をどのように広げていくかということを検討しています。ECでBtoCで売りたいけれど、ノウハウがないという会社も多いので、イコリスの知見を活かして何かできないかと考えています。また、全く予想外のデジタル分野のビジネスを持ち込んでくれる方も多く、そのような案件も検討しています。
取材者: 全方位でいろいろ検討されているのですね。
取材者:最後に、貴社の創業の経緯や創業時の思いについてお伺いできますでしょうか?
回答者: はい。創業は1971年で、加藤という者が創業した会社です。当時は「カトー特殊計紙」という社名で、特殊な紙を製造販売していました。この頭文字がKTKという社名の由来です。
その後、Windows95が登場した頃にレーザープリンターが普及し始め、レーザープリンター用トナーのリサイクルビジネスを始めました。その前は、リサイクルリボンを製造していました。これは、銀行のATMで通帳記入する際などに使用されるリボンです。リボンのリサイクルから始まり、今ではインクなどもリサイクルしています。
ケイティケイ単体で2006年にJASDAQに上場しました。その後、文具卸売業の青雲クラウンと株式交換という形で一緒になり、青雲クラウンのオーナー社長である青山がケイティケイの経営も見るようになりました。
取材者: なるほど。ECサイトで文具を幅広く販売できるようになったのは、青雲クラウンの影響もあるのですね。
回答者: はい、そうです。青雲クラウンは歴史のある文具問屋で、商品ラインナップが豊富です。KTKはトナーに特化していたので、文具に関しては青雲クラウンの力を借りることができました。両社にとって大きなシナジー効果がありました。
専務取締役管理本部長兼グループ戦略本部長 葛西裕之様
ー
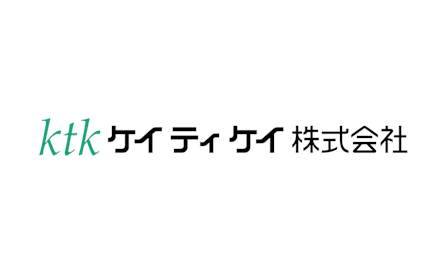
ケイティケイ(株)
東証STD、名証メイン 3035
決算:8月20日
CP&X
【2026年8月期1Q】
【サマリー】
決算概要
当四半期においては、利益率が高い自社製品の拡販やPC販売等の増加により、前年同期比で増収増益を達成。自社製品の拡販においては、重点施策として取り組んできた新規営業活動の成果が現れ始めたことが、大きく貢献。また、リユーストナーの市場再編が進行する中で、当社の製造直販型の安定した供給・品質管理体制と強固な顧客基盤が、優位性を発揮。加えて、IT関連でもWindows11への切り替え需要によるPC販売等が引き続き好調に推移したことで、サプライ事業・ITソリューション事業ともに前年同四半期比で増収増益。
これらの結果、当四半期の売上高は4,715,605千円(前年同期比8.5%増)、営業利益は105,042千円(前年同期比62.5%増)、経常利益は135,336千円(前年同期比44.0%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は83,329千円(前年同期比47.6%増)となった。
セグメント別または事業別の増減要因
(サプライ事業)
重点的に推進してきた新規営業活動が奏功したことで、自社製品の拡販が順調に推移し、特に利益が大きく伸長。これらの結果、売上高は3,541,789千円(前年同期比5.5%増)、セグメント利益は222,605千円(前年同期比26.3%増)となった。
(ITソリューション事業)
Windows11への切り替え需要によりPC販売等が好調に進み、増収増益。これらの結果、売上高は1,173,815千円(前年同期比18.4%増)、セグメント利益は34,518千円(前年同期比26.2%増)となった。
通期見通しと進捗率・達成可能性
進捗率は、売上高24.4% 営業利益22.3%、経常利益24.6%、EBITDA24.4% 親会社株主に帰属する四半期純利益23.8%と、概ね順調に推移。
トピックス
(サプライ事業)
市場再編が進行する中でも、当社のリユーストナー販売本数は増加し、売上・利益に貢献。
(ITソリューション事業)
Windows11への切り替え需要に応じたPC販売が増加し、スキャニングサービス案件も増加。
Add a Title
取材アーカイブ
CP&X
【2025年8月期(通期)】
決算概要
サプライ事業の復調とIT特需により売上・営業利益が伸長
2025年8月期の業績は、売上高18,927百万円(前期比4.5%増)、営業利益426百万円(同11.3%増)、経常利益515百万円(同5.4%増)、当期純利益332百万円(同3.8%減)での着地。主力のリユーストナー等を扱うサプライ事業が、長年の横ばい傾向から脱却し増収増益基調へ転換したことが寄与。ITソリューション事業においても、Windows 11への移行に伴う特需を確実に取り込み、全社業績を牽引。
セグメント別または事業別の増減要因
競合撤退による残存者利益とPC特需の捕捉
サプライ事業は、既存顧客維持に加え新規開拓営業へ注力した成果が発現したほか、リユーストナー事業における「残存者利益」の影響により販売本数が増加。ITソリューション事業は、Windows 11移行に伴うPC入替特需を入り口とし、ネットワークやセキュリティ等の付帯サービス提供へ繋げたことが奏功。加えて、提携先新興企業のSaaSやアプリ(エンゲージメント関連等)のクロスセル販売も伸長。
主要KPIの進捗と変化
トナー販売本数の増加とIT人材採用の改善
サプライ事業における重要指標であるトナー販売本数は、競合環境の変化(撤退)を背景に増加基調で推移。人材戦略においては、新卒採用(年平均4〜5名)の継続に加え、中途採用にて首都圏手当拡充等の給与改定を実施した結果、応募反応が良化。IT領域ではスタートアップ企業との連携強化により、他社製サービスの販売機会数が増加傾向。
季節性・一過性要因の有無と影響
特段の損失要因はないもののPC特需一巡を想定
当期の業績を大きく毀損するような一過性の損失要因は特段見当たらないとの認識。ただし、ITソリューション事業の好調要因となったWindows 11移行に伴うPC入替需要は特需的な側面が強く、今後は需要一巡による伸び悩みのリスクを内包。今後の成長維持には、特需を契機としたストック型サービスや付帯サービスの積み上げが鍵となる構造。
通期見通しと進捗率・達成可能性
前期の延長線上での着実な成長と課題完遂を志向
2026年8月期の業績予想は、基本的に2025年8月期の延長線上と位置づけ、サプライ事業での微増(増収増益)確保とITソリューション事業による成長牽引を目指す方針。前中期経営計画における未完遂の課題に対し、新たなテーマへの移行ではなく「積み残し課題の確実な仕上げ」を重視して取り組む計画。株主還元は配当性向30%を目処とし、前期比1円増配の年間18円(4期連続増配)を予想。
トピックス
障がい福祉事業のM&Aによる業務内製化とコスト削減
2025年7月に障がい福祉事業を行う株式会社じぶんスペースをグループ化し、2026年8月期より連結対象化。同社の売上規模は限定的であるものの、ITスキルを保有する事務局社員や利用者を活用することで、従来外注していた業務の内製化によるコスト削減およびIT事業の人材工数増加といったシナジーを期待。IT関連事業強化に向けたスタートアップ企業との関係深化も継続中。
【2025年8月期(通期)】
Q:成長戦略のポイント(今後の取り組みやトピックス、計画にない新たな戦略的施策等を含む)はなんでしょうか?
A:成長事業と位置付けているITソリューション事業の拡大が主軸となります。具体的な成果として、提携関係にある新興企業が開発したアプリやSaaS系サービス、特にエンゲージメント関連のサービスなどを当社がクロスセルで販売する機会が増加しており、こうした取り組みを継続します。また、人材採用に関しては、新卒採用に加えて中途採用を強化するために首都圏での手当を拡充する給与改定を実施しました。これに対する反応は良好であり、今後は特に首都圏での増員に向けた採用活動を活発化させ、事業成長の基盤を固めていく方針です。
Q:成長戦略のポイントについて、前提条件等での変化とその影響等をご説明ください。
A:主力であるサプライ事業(トナー・文具等)において、長らく続いていた横ばいの状況から増収増益基調へと反転したことが大きな変化です。これは、既存顧客の維持だけでなく新規営業活動に注力した効果が現れたことによるものです。加えて、リユーストナー事業における「残存者利益」として販売本数が増加していることも好調の要因となっています。一方で、ITソリューション事業に関しては、Windows 11への移行に伴うパソコン入れ替え特需が一巡することで、今後は伸び悩む可能性も想定していますが、ネットワークやセキュリティなどの付帯サービス提供につなげることで成長維持を図ります。
Q:通期予想の戦略と施策についてご説明ください。
A:2026年8月期の業績予想については、大枠として2025年8月期の延長線上にあると考えています。基盤ビジネスであるサプライ事業については、現在の好調な状況を維持しつつ微増(増収増益)を確保する計画です。その上で、基本的にはITソリューション事業によって全体としての成長を目指すという構造で業績を予想しています。
Q:受注・競合状況は如何でしょうか?
A:サプライ事業においては、主力のリユーストナー事業で、いわゆる「残存者利益」の一部が出ているものと認識しており、その影響を含めて当社のトナー販売本数が増加している状況にあります。また、これまで十分に対応できていなかった新規開拓営業に注力したことで、予想以上の成果と手応えを感じています。ITソリューション事業では、Windows 11への移行に伴うパソコン特需があり、それを入り口とした関連サービスの受注につながりました。
Q:M&A、業務提携、事業売却などの実施または検討状況と、それに伴う影響についてご説明ください。
A:2025年7月に障がい福祉事業を行う株式会社じぶんスペースをグループに迎え入れ、2026年8月期から連結対象となります。対象会社の売上規模は大きくないため、連結売上・利益への直接的な貢献は限定的ですが、同社の事務局社員や利用者の多くがITスキルを保有している点にシナジーを見出しています。これまで外部に委託していた業務の一部を内製化することで直接的なコスト削減効果が見込めるほか、ITソリューションビジネスに携わる人材の工数増加にもつながるため、ITソリューション事業を伸長させる基盤が整ったと考えています。また、IT関連事業の強化に向けてスタートアップ企業との関係を深めており、新興企業のサービスを当社が販売するクロスセル等の成果が出始めています。
Q:中期事業計画の内容や進捗状況等をご説明ください。
A:基本的には前中期経営計画の延長線上での取り組みを進めていく方針です。前計画において完遂できていない課題や積み残しがあるため、次々と新しい課題へ移行するのではなく、これらの積み残した課題を確実に仕上げていくことを重視しています。したがって、2025年以降に向けた取り組みも、これまでの経営計画の継続と深化であると捉えています。
Q:株主還元の方針をご説明ください。
A:株主還元の方針に変更はなく、配当性向30%を目処としています。進行期については、前期比1円増配の年間18円を予想しており、これで2023年以降4年連続での増配となる見込みです。着実な増配を継続することこそが株主の皆様への最良のメッセージであると考えており、今後もこうした増配傾向を継続していく意思を持っています。
【2025年8月期(通期)】
取材者:初めに、2025年8月期の決算状況をお聞かせいただけますか。
売上高は18,927百万円で前年度比4.5%増、営業利益は426百万円で前年度比11.3%増、経常利益は515百万円で前年度比5.4%増、当期純利益は332百万円で、前年度比3.8%減です。
目標を達成し、好調な決算と拝見しました。増減要因をご説明いただけますか。
回答者:セグメント別にご説明します。サプライ事業、すなわちトナーや文具などの事業と、成長事業であるITソリューション事業の双方が好調でした。サプライ事業は、主力である自社製造のリユーストナーにおいて、新規営業活動の効果が現れ、売上が伸長しました。これまでの横ばい、踊り場の状況から反転した点が、増収増益の要因です。ITソリューション事業は、Windows 11への移行に伴うパソコン特需が要因です。パソコン導入を入り口に、ネットワークやセキュリティなどのサービス提供につなげられた点が、好調の主な理由と考えています。
取材者:第2四半期はITソリューションが好調でしたが、下半期はサプライ事業も伸長したイメージですか。
回答者:その通りです。ITソリューションは、パソコン入れ替え特需の一巡により伸び悩む可能性がありますが、通期決算についても前回お話しした要素と同様です。サプライ事業は長らく横ばいが続いていましたが、新規営業活動の効果が予想以上にあると手応えを感じています。従来そこまでできていなかったという実態があるのですが、既存顧客の維持に重きを置き、新規開拓が滞っていましたが、注力した成果が出ています。また、リユーストナー事業における「残存者利益」も出てきており、その影響を含めてトナーの販売本数が増加している状況です。
取材者:前回、IT関連事業の強化に向けてスタートアップ企業との関係を深めるというお話がありましたが、成果や業績につながるものはございますか。
回答者:根本的な成果はこれからですが、分かりやすい成果として、新興企業が開発したアプリやSaaS系サービスを、当社がクロスセルで販売するケースが増えています。具体的には、エンゲージメント関連のサービスなどで、ご購入いただく機会が増えていると実感しています。
取材者:7月に株式会社じぶんスペースをグループインしたとのニュースがありましたが、影響はいかがですか。
回答者:前期、2025年8月期への影響はありません。進行期である2026年8月期から連結対象となります。事業内容は障がい福祉事業であり、現状の売上規模は大きくないため、M&Aによる売上・利益への貢献は限定的です。ただし、じぶんスペースの事務局の社員や利用者の多くがITスキルを保有しています。これまで内部で対応できず外注していた業務の一部を内製化することで、直接的なコスト削減効果が期待できます。また、ITソリューションビジネスに携わる人材の工数増加にもつながるため、ITソリューション事業を伸長させる基盤が整ってきたと考えています。
取材者:採用数の推移はいかがですか。
回答者:順調とは言えませんが、新卒と中途の両面で進めています。新卒採用はグループ全体で毎年コンスタントに平均4〜5名を採用しています。中途採用は難しい状況でしたが、今期(進行期)に入り、首都圏の手当を拡充する給与改定を行いました。その結果、反応が良くなっており、今後は特に首都圏での増員に向けて採用活動を活発化したいと考えています。
取材者:今期の業績に影響を与えたような一過性の要因はございますか。
回答者:特に見当たりません。
取材者:2026年8月期の業績予想について、見通しはいかがですか。
回答者:大枠として、2025年8月期の延長線上で考えています。基盤ビジネスであるサプライ事業は微増(増収増益)を維持し、基本的にはITソリューション事業で成長を目指す予測です。
取材者:今期、新たに取り組む重要施策はございますか。
回答者:基本的には前中期経営計画の延長線上であり、積み残した課題への取り組みとなります。課題を完遂できていない部分があるため、新しい課題へ次々と移行するのではなく、積み残しを確実に仕上げていく認識です。
取材者:2025年中期経営計画に向けての取り組みと捉えてよろしいですか。
回答者:その通りです。
取材者:株主還元の方針に変更はございますか。
回答者:変更はありません。配当性向30%を目処とし、今期(進行期)は前期比1円増配の年間18円を予想しています。2023年以降、4年連続で1円ずつの増配となりますが、着実な増配を継続することが、株主の皆様への最良のメッセージになると考えています。今後もこうした傾向を継続したいという意思を表明しています。
取材者:その他、足元の状況についてトピックスやニュースリリースはございますか。
回答者:特にありません。
専務取締役管理本部長兼グループ戦略本部長
葛西 裕之 様
Add a Title
取材アーカイブ
CP&X
決算概要2025年8月期第2四半期の売上高は91億6,400万円と前年同期比5.9%の増加、営業利益は1億6,600万円と前年同期比12.7%の増加、経常利益は2億1,800万円と前年同期比4.7%の増加、中間純利益は1億3,700万円と前年同期比13.7%の減少となった。中間純利益の減少は、当中間期において政策保有株式の売却が少額に留まったことが要因である。全体として、ITソリューション分野の伸びが業績を牽引している状況である。
セグメント別または事業別の増減要因
売上高は主にITソリューションセグメントが伸長している。営業利益はITソリューションセグメントが前年同期比131%と大幅に増加した一方、基盤事業であるサプライセグメントは同97%であった。ITソリューション事業はパソコン関連を含め、Windows関連が好調に推移しており、ビジネスにとって良い状況である。
主要KPIの進捗と変化
当社は、直接的なKPIとして特定の数値を挙げてはいないものの、ITに関連する事業機会を捉えるための重要な取り組みとして、スタートアップ企業との交流を積極的に行っている。これは、自社の感覚をアップデートし、世の中に増えている実用的なテクノロジーをお客様への提供や社内展開に繋げる可能性を模索するためである。
季節性・一過性要因の有無と影響
今期の業績に影響を与えるような季節性または一過性の大きな要因はない。当社のビジネスは、個別の大型案件よりも、小口取引を継続的に積み上げていく事業構造であるため、一過性の要因が出にくい特性を持つ。
通期見通しと進捗率・達成可能性
通期見通しに対する進捗率は、中間期まではおおむね予算の範疇であると認識している。中期経営計画の達成はITソリューション事業の成長にかかっており、IT人材の確保やIT関連への取り組みを通じて、非連続とまではいかないまでも着実に成長を目指していく方針である。
トピックス
トピックスとしては、コスト削減ニーズの高まりを背景に、リユース・リサイクルトナーの優位性が再評価されている点がある。当社のリユース品は純正品の約3分の1の価格で提供可能であり、他社製品と比較してもさらに3割程度安価に提供できるという価格競争力を持つ。これは自社工場で製造していることに起因する。
加えて、S.P.P.(サステナブルパートナープログラム)を展開している。これは、トナーカートリッジにQRコードを付与し、工場出荷時、回収時、顧客による装着時にQRコードを読み取ることで完全なトレーサビリティを確保するものである。これにより、プラスチック廃棄量の削減やCO2排出量の削減といった環境貢献度を数値化し、環境貢献レポートとして顧客企業に提供することが可能である。このプログラムは、コスト削減と環境貢献の両面から顧客に価値を提案するものであり、経営層への訴求力も高い注目点である。
Q:成長戦略のポイント(今後の取り組みやトピックス、計画にない新たな戦略的施策等を含む)はなんでしょうか?
A:当社はITソリューション分野の成長に注力しており、特にWindows環境を含めたパソコン関連のビジネスが好調に推移しています。また、環境に配慮したリユース・リサイクルトナーの事業も重要な柱と位置づけています。特に、純正品の3分の1程度の価格で提供できるリユース品は、コスト削減を求める製造業などの企業にとって大きなメリットとなっており、環境負荷低減にも貢献できる点を強化して提案していく方針です。
さらに、S.P.P.(サステナブルパートナープログラム)という独自の取り組みを推進しています。これは、使用済みトナーカートリッジにQRコードを付けて管理することで、回収からリユースまでのトレーサビリティを確保し、顧客がどれだけプラスチック廃棄量やCO2排出量を削減できたかを数値で可視化してレポートするものです。これにより、現場の担当者から経営層まで、企業の様々な階層に対して環境貢献とコスト削減の両面で価値を訴求し、プログラムへの参加を促しています。
Q:M&A、業務提携などの実施または検討状況と、それに伴う影響についてご説明ください。
A:具体的なM&Aや業務提携の案件は現時点ではありませんが、IT分野、特に中小企業や小規模事業者が受け入れやすい「泥臭いIT」と表現されるような、入り口となる技術や人材を持つ企業との提携やM&Aを検討していきたいと考えています。これは、当社のビジネスモデルが、個別の大きな案件よりも、きめ細かいサービスを継続的に提供することで成り立っているため、一過性の要因に左右されない事業基盤の強化を目指すものです。
Q:中期経営計画の内容や進捗状況等をご説明ください。
A:現段階では、今回の業績開示の通り、予算組通りに進捗しており、新しい中期経営計画の1年目としては順調に進んでいると認識しています。中期経営計画の達成は、ITソリューション分野がどれだけ成長できるかにかかっています。当社は、M&Aなども含めてIT人材の確保やIT関連への投資を積極的に行い、「非連続の成長」とまではいかないまでも、着実にITソリューション事業を伸ばしていく方針です。8月20日の決算をしっかり達成し、次期に向けてこれらの取り組みを本格化させていく考えです。
Q:株主還元の方針をご説明ください。
A:株主還元については、配当性向30%までを着実に目指すという方針に変わりはございません。これまでも継続的に増配を実施しており、来期以降のことについては現時点では明確な言及は控えますが、30%という目標を掲げている以上、それに向かって着実に実行していく方針です。
また、当社の株主の約97%が個人投資家であるため、配当だけでなく株主優待を望まれる声も多くございます 。そのため、優待制度をより利用しやすいように、昨年度から単元株数を引き下げるなどの変更を行いました。配当の増額と並行して株主優待の充実も図ることが、当社の企業規模において重要な株主還元策であると考えております。
取材者:まず初めに、2025年8月期の第2四半期決算についてお伺いいたします。売上高は91億6,400万円で前年同期比5.9%増加、営業利益は1億6,600万円で前年同期比12.7%増加、経常利益は2億1,800万円で前年同期比4.7%増加、親会社株主に帰属する中間純利益は1億3,700万円で前年同期比13.7%減少とのことですが、かなり好調に業績が推移しているように見受けられます。これについての業績増減要因をご説明いただけますか?
回答者:好調という認識はございません。ITソリューションは一部伸びており、パソコン関連を含め、Windowsの分野も弊社のビジネスにとっては良い状況にあります。売上は主にITセグメントが伸びています。決算資料にも記載しましたが、セグメント別の営業利益ではITソリューションが131%と伸長している反面、基盤であるサプライ事業は97%です。経常利益に関しては、自社サイト「YORIDORI」の開発に伴う減価償却費や、人件費の増加が影響しています。一部IT人材への先行投資も含め、これらの費用が営業利益段階でも関連してきています。また、借入金は少ない方ですが、金利なども少しずつ影響してきています。純利益に関しては、投資有価証券の売却益がありましたが、これは元々織り込み済みです。
取材者:そうしますと、中間予想に対する進捗率はいかがですか?
回答者:数字に関しては、本来であればもっと上を目指したいという気持ちはありますが、第3四半期に割と大きな数字を抱えていることも事実です。中間期までは、予算比に関しても一部営業利益は耐えきれていませんが、概ね想定の範囲内だと考えております。
取材者:その他、今期のここまでの業績に関して、季節的要因や一過性の要因はございましたか?
回答者:一過性の要因は特にございません。
取材者:それは会社全体として見ても、一過性の要因が出にくいということですか?
回答者:良い意味で大きな案件は欲しいところではありますが、弊社のビジネスは細かいものを継続的にご購入いただく商売が多いです。逆に一時的な要因が出ると反動も来てしまうため、現状で妥当だと考えております。
取材者:先ほどIT人材のお話が出ましたが、前期と比較して人材採用数の推移はいかがですか?
回答者:IT人材はもっと採用したいのですが、なかなか確保できていません。ITセグメントに配属された若手はおりますが、IT人材にまではまだ育っていません。
取材者:そこの育成の部分はこれからですね。
回答者:はい。
取材者:IT人材をより採用していくために、何か行われている施策や方針はございますか?
回答者:具体的な話ではありませんが、M&Aなどを通じて会社全体で人材を確保したいという思いはあります。しかし、なかなか良い話はありません。
取材者:中期経営計画に対する進捗度合いはいかがですか?
回答者:現段階では、今回の通期に関しては、予算通りに推移していると考えておりますので、新しい中期経営計画の1年目は、まず達成できるのではないかと思っております。中期経営計画の達成は、ITソリューションが着実に成長するかにかかっています。大きな意味ではありませんが、非連続の成長とまではいかないまでも、人材確保やIT関連への投資などを積極的に行い、伸ばしていきたいと考えております。弊社は8月20日決算ですので、それをきちんと達成した上で、次期にはそういった取り組みを色々行っていきたいと考えております。
取材者:M&Aなどに関して、業務提携も含め、実施のご予定や検討状況、あとは方針についてございましたら、答えられる範囲で教えていただけますか?
回答者:具体的なことはございませんが、ITおよびITを冠するようなことについては取り組んでいきたいと考えております。もう少し話をすると、我々がターゲットとしている中小企業や小規模事業者は、最新のITを提案してもすぐに受け入れてもらえるわけではありません。もう少し実用的なITというか、企業の生産性を向上させるための入口は他にもあると考えております。はっきり言うと、企業にとってはIT投資なのですが、少し遅れて導入されるような分野もあります。そういったところに、リーチすることが出来る技術や人材を持った企業に、ぜひ仲間になってもらいたいと考えております。
取材者:そうすると、かなり幅広い視点から業務提携を含めて検討されているイメージですか?
回答者:その通りです。
取材者:恐れ入ります。その他、貴社にとって主要なKPIはございますか?
回答者:KPIというわけではないのですが、ITに関連して、なるべくスタートアップの方々には会うようにしています。弊社とは全く無関係だろうという人も含めてです。そういった方々の空気を吸いたいという思いがあります。それが直接繋がることはないかもしれませんが、まずはそういったことを踏まえて、我々の感覚をアップデートしていかなければならないと考えております。ITに限らず、テクノロジーというと大げさですが、最先端の話は到底分かりませんが、世の中には実用的なものが増えてきています。そういったものを見て、お客様への提供なのか社内への展開なのかは分かりませんが、それは必要だと感じております。
取材者:そうすると、そういったことがうまく繋がっていくと、中期経営計画のその先も含めて、何か大きなことができそうですね。
回答者:アンテナを張るというか、そういったところは数値化しにくい面もありますが、逆にチャンスが広がったように感じています。
取材者:株主還元の方針について教えていただけますか?
回答者:配当性向は30%まで着実にという方針で、これまでも増配を続けてきておりますので、来期以降のことは現時点ではお話しできませんが、30%という目標を掲げている以上、それに向かって着実に実行していくという方針に変わりはございません。また、弊社の株主のほぼ97%が個人投資家ですので、還元策としては株主優待を望まれる方も多いです。優待制度をより利用しやすいように、昨年度から単元株数を引き下げるなど変更しております。配当を上げつつ優待を充実させることも、弊社の企業規模においては考えていることです。
取材者:承知いたしました。最後に、足元の状況につきまして、トピックスやニュースリリースがございましたら教えていただけますか?
回答者:ニュースというわけではありませんが、いわゆるトランプ関税の影響で、企業の特に製造業はコスト削減をさらに強化しようという動きが強まっています。私どものリユース、リサイクル製品は環境に優しいだけでなく、コスト削減も実現できます。一般的に環境に良いものは価格が高いというイメージがありますが、そうではありません。例えば、純正品トナーとリユース品のトナーでは、価格が約3分の1になります。例えばアスクル様に掲載されている価格よりも、さらに3割ほど安く提供できるのです。弊社は自社工場で製造しておりますので、それが可能です。環境に配慮しつつコスト削減を求める企業に対して、再度提案を強化していきたいと考えております。これは弊社の強みとなる反面、きちんと推進していきたいと考えております。
取材者:確かにそれは、他社との差別化、価格も含めて、かなり期待できそうですね。
回答者:例えばアスクル様に掲載されている商品をアスクル様よりも3割安く提供できる会社は他にあまりないと思います。
取材者:それは今後かなり大きなトピックスになりそうですね。その他何かトピックスはございますか?
回答者:あとは、ホームページでも展開しておりますが、弊社の「SPP(サステナブルパートナープログラム)」についてです。トナーの本体ではなく、箱にQRコードがついています。リユースは使用済みカートリッジをどうするかが重要になります。企業では、トナーの箱に入ったものが在庫として保管されていることが多いです。しかし、実際に箱を開けて、黒いプラスチック製のトナーカートリッジを見るのは、トナー交換時以外にはあまりないと思います。使い終わったものをどうしているかというと、購入時に返却しているという認識はあるものの、きちんと返却されているかまでは把握できていないのが現状だと思います。私どもが企業の経営層や責任者の方とお会いする際には、あえてトナーの本体を持っていくようにしています。箱を開けて、トナーを手に取っていただくと、その重さやプラスチックの感触を感じていただけます。この重たいプラスチックのものをQRコードで管理し、確実に回収し、きちんとリユースして再利用するのだと説明する際、提案書だけを見せるのと、実際に持ってもらうのとでは、伝わり方が違うと考えております。
弊社工場から出荷する際にこのQRコードを読み込み、工場に返却される際も読み込みます。お客様の方でもトナー交換時にQRコードを読み込んでいただくことで、完全なトレーサビリティが確保できます。これにより、使う側の責任も含めて、使用済みのものを確実に返却し、それが再び戻ってくるというサーキュラーエコノミーの概念をお客様と弊社双方で納得できる形で実現します。このサステナブルなプログラムにぜひご参加いただきたいと考えており、当然、お値段も優遇させていただきます。
取材者:今まで見えていなかった部分が可視化されるようなイメージでしょうか?
回答者:はい。価格も安くなるだけでなく、このプラスチックを例えば5回使用することで、5回分の新しいプラスチックを製造する必要がなくなります。これにより、プラスチックの使用量を削減できるのです。その結果を基に、CO2排出量をこれだけ抑えられたという、プラスチック廃棄量の削減とCO2の削減も数値化できます。現場の方にはスキャンしていただくことでポイントが貯まり、ちょっとしたお菓子を差し上げるような仕組みも考えております。課長さんクラスの方には、自動発注も可能で、非常に便利だとお伝えしています。年に1~2回、経営層にはこれだけのCO2削減量を達成したという環境貢献レポートを提出できます。そういった形でプログラムをきちんとご提案していくことを考えております。
取材者:どこの層にも何か刺さるような仕組みになっているのですね。本当にその環境のレポートは経営層にかなり刺さりそうなものですね。
回答者:会社の中で、CO2削減を数値化できるものはあまりありません。正直、1本当たりの削減量は小さいですが、小さくてもプロジェクトとして可視化でき、数値化できるということが重要だと考えております。
代表取締役社長 青山 英生様
取材アーカイブ
ビジネスモデルや事業内容
ケイティケイは、リサイクルトナーの製造販売を基盤とするサプライ事業と、中小企業向けのITソリューション事業を展開しています。ペーパーレス化の流れに対応するため、複合機などお客様のニーズに合わせたITソリューションの提供に力を入れている。また、近年はECサイト「YORIDORI(ヨリドリ)」を立ち上げ、デジタルマーケティングにも注力。これは、グループ会社のイコリスの知見を活かしたもので、売上増加にも貢献しつつある。さらに、既存顧客の囲い込みとリサイクルトナーカートリッジのトレーサビリティ強化を目的としたサステナブルパートナープログラムを導入。これは、トナーカートリッジにQRコードを貼ることで、回収と発注を効率化する仕組みである。
創業の経緯と転機となった出来事
創業は1971年で、当初は特殊紙の製造販売を行っていた。その後、レーザープリンターの普及に伴い、トナーのリサイクル事業を開始し、現在に至る。
特徴や強み
ケイティケイはリサイクルトナーの製造メーカーであり、製造直販を行っているという強みを持つ。 これは、リサイクルトナー業界では数少ないビジネスモデルであり、顧客のニーズに合わせた柔軟な対応を可能にしている。 また、グループ会社である青雲クラウンとのシナジー効果により、文具の販売においても幅広い商品ラインナップを提供できることが強みとなっている。
成長戦略
ケイティケイは、デジタルマーケティングを強化することで、ECサイト「YORIDORI(ヨリドリ)」の売上増加を図っている。 また、サステナブルパートナープログラムを導入し、既存顧客の囲い込みとリサイクルトナーカートリッジのトレーサビリティ強化を推進している。 さらに、M&A戦略として、サプライ事業では事業承継を目的とした小規模なM&Aを、ITソリューション事業ではEC事業やデジタル分野でのM&Aを検討している。
Q:事業内容やビジネスモデル、特徴や強みなどをご説明ください。
A:当社の基盤事業はサプライ事業です。 特徴としては、自社でリサイクルトナーを製造しているメーカーであるという点が挙げられます。 オフィスに必要なものとしてリサイクルトナーを販売する中で、紙や文具、オフィスの家具など、事務所で必要なものは一式販売しており、自社製品とともに仕入れ商品も販売しています。 自社製品は粗利益率が高く、それを基幹商品としてサプライ事業を展開しています。 これが創業以来の基本的なビジネスモデルです。
グループ全体で1万数千社のお客様とトナーを中心に取引をしています。 しかし、ペーパーレス化の流れの中で、お客様のニーズが変わってきました。 かつてはプリンター専用機が各社にありましたが、近年では複合機に集約されるケースが増えています。 なお、当社が販売しているリサイクルトナーはプリンター専用機のためのものです。 複合機はメーカーが純正トナーをカウンター料金制度で提供しているため、当社のリサイクルトナーを販売する余地はありません。
プリンター専用機から複合機への集約など、デジタル化やペーパーレス化の流れの中で需要が変わってきており、それに対応するのがITソリューション事業です。 お客様の中には、「プリンターはいらないけど複合機の買い替えをしたい」という方もいます。 また、パソコンやセキュリティなど、複合機に付随する様々なニーズにも対応しています。
基本的には顧客基盤は共通で、お客様のサプライとITソリューションの両方を契約いただいているケースも多いです。 ITソリューション事業のお客様は中小企業が中心で、従業員50人以下の企業が多いです。 情報システム部門を自社で抱えているような大企業は、お客様にはなりにくいです。 中小企業の情報システム部門の代行や、情報システム担当者を支援するような形でサービスを提供しています。 複合機を起点に、様々な提案や支援をしています。
Q:複合機、プリンター専用機から複合機に変えられるような提案も行っているのでしょうか?
A:プリンター用のリサイクルトナーが当社にとって主力の商品ですので、基本的にはそれを守るというスタンスです。 しかし、例えば「プリンターはいらないから複合機に統合したい」というお客様に対しては複合機の提案も行えるように、全方位の対応をしています。
Q:サプライ事業の中で新たに立ち上げたECサイトについて詳しくご説明いただけますでしょうか?
A:元々「はっするネット」というECサイトを持っていたのですが、これは受発注システムのようなものでした。 Google検索などで外部からお客様が流入してくるようなオープンサイトではなく、既存のお客様にFAXで注文するよりも便利にご利用いただくためのサイトでした。
それを昨年「YORIDORI(ヨリドリ)」というECサイトに一新しました。 これはオープンサイトになっており、外部からの集客もできるようになりました。 既存のお客様のユーザビリティ向上も図り、外部のお客様と既存のお客様の両方から購買を促進することで、客単価の向上を目指しています。
また、「YORIDORI(ヨリドリ)」はデジタルマーケティングのプラットフォームとしても活用しています。 サイトでは様々な商品の紹介だけでなく、ITソリューションに誘導するような記事なども掲載しています。
Q:デジタルマーケティングを主導できるようになったのは、グループ化したイコリスの影響でしょうか?
A:はい、そうです。 元々デジタルマーケティングを強化していこうという方向性があった中で、M&Aの話があり、現在はイコリスを中核にケイティケイにもデジタルマーケティングの部署を設け、昨年8月からWebマーケティングを強化しています。
Q:売上高増加要因としてデジタルマーケティングの伸長がありましたが、現状はイコリスの知見が社内に活かされているということでしょうか?
A:現状、実際に売上利益に直結しているのはイコリスです。 決算説明資料などでもITソリューションの中でイコリスのサプリメントや化粧品販売の話に触れておりますが、現時点ではそちらの貢献が大きいです。
外部からの集客など、イコリスの知見を生かして「YORIDORI(ヨリドリ)」を運営しており、サプライ事業の売上にも貢献しつつあります。
Q:サプライ事業で新規営業活動に対する取り組みについて教えていただけますでしょうか?
A:これはシンプルに言って、コロナ禍で対面型の営業活動が停滞したため、アフターコロナで改めて営業を強化しているということです。
特に東京では、新規の営業活動が難しくなっていました。 当社のリサイクルトナーのメインのお客様は、都心のオフィスだけでなく、製造業、病院、介護、物流などの業界にも多くいます。 これらの業界のお客様に対しても、コロナ禍で営業活動が制限されていました。 病院などは、なかなか電話やメールでは対応できず、実際に行かないと話ができないところが多いのが現実です。
Q:サプライ事業に関しまして、サステナブルパートナープログラムについてご説明いただけますでしょうか?
A:これは端的に言うと、既存のお客様の囲い込み戦略です。 新規顧客獲得も重要ですが、既存顧客の囲い込みも重要です。 また、リサイクル業者としての責任を果たすという側面もあります。 リサイクルは、トナーカートリッジを回収し、再生して販売するというサイクルを回さなければいけません。 しかし、現実には販売したトナーカートリッジを回収できないケースも多いのです。
他の業者に回収されてしまったり、逆に当社が回収する中に売ってないものが含まれていたりするなど、様々な問題があります。 そこで、リサイクルカートリッジのトレーサビリティを強化するために、このサステナブルパートナープログラムを導入しました。
具体的には、トナーカートリッジにQRコードを貼っています。 お客様がトナーを交換する際に、新しいトナーのQRコードを読み取ってもらうことで、古いトナーが返ってくるということがわかるようになります。 そして、それを回収に伺います。 お客様のニーズによっては、自動的に発注も行えます。
お客様にとっては、発注や在庫管理の手間が省けます。 当社にとっては、QRコードを読み取っていただくことで、回収と同時に次のトナーも自動的に発注いただけることになります。
Q:IoT的な側面があるのでしょうか?
A:はい。 リサイクルトナーの会社は、ほとんどが販売店を介したビジネスを行っています。 当社は数少ない製造直販です。 ですので、QRコードで回収や発注ができる仕組みを作れるというメリットがあります。 この辺を今後推進していきたいと考えています。
Q:貴社はおそらくM&Aなどの戦略もあるかと思いますが、M&Aの戦略として何か、こういう企業をターゲットにしているというのはございますか?
A:まず、全方位で情報を集めています。 サプライ事業においては、例えば同業の文具販売店などで、社長が高齢になり事業承継できず、どこかに事業を譲渡したいというケースが増えています。 そのようなケースでは、M&Aというよりも、お客様を引き継ぐというような形になります。 少なくとも仲介業者は入らないような、リリースなども出さないM&Aです。
ITソリューション分野では、例えばイコリスのEC事業をどのように広げていくかということを検討しています。 ECでBtoCで売りたいけれど、ノウハウがないという会社も多いので、イコリスの知見を活かして何かできないかと考えています。 また、全く予想外のデジタル分野のビジネスを持ち込んでくれる方も多く、そのような案件も検討しています。
Q:最後に、貴社の創業の経緯や創業時の思いについてお伺いできますでしょうか?
A:創業は1971年で、加藤という者が創業した会社です。 当時は「カトー特殊計紙」という社名で、特殊な紙を製造販売していました。 この頭文字がKTKという社名の由来です。
その後、Windows95が登場した頃にレーザープリンターが普及し始め、レーザープリンター用トナーのリサイクルビジネスを始めました。 その前は、リサイクルリボンを製造していました。 これは、銀行のATMで通帳記入する際などに使用されるリボンです。 リボンのリサイクルから始まり、今ではインクなどもリサイクルしています。
ケイティケイ単体で2006年にJASDAQに上場しました。 その後、文具卸売業の青雲クラウンと株式交換という形で一緒になり、青雲クラウンのオーナー社長である青山がケイティケイの経営も見るようになりました。
Q:ECサイトで文具を幅広く販売できるようになったのは、青雲クラウンの影響もあるのでしょうか?
A:はい、そうです。 青雲クラウンは歴史のある文具問屋で、商品ラインナップが豊富です。 KTKはトナーに特化していたので、文具に関しては青雲クラウンの力を借りることができました。 両社にとって大きなシナジー効果がありました。
取材者: 事業内容やビジネスモデル、特徴や強みなどをご説明ください。
回答者: 当社の基盤事業はサプライ事業です。特徴としては、自社でリサイクルトナーを製造しているメーカーであるという点が挙げられます。オフィスに必要なものとしてリサイクルトナーを販売する中で、紙や文具、オフィスの家具など、事務所で必要なものは一式販売しており、自社製品とともに仕入れ商品も販売しています。自社製品は粗利益率が高く、それを基幹商品としてサプライ事業を展開しています。これが創業以来の基本的なビジネスモデルです。
グループ全体で1万数千社のお客様がいらっしゃいまして、トナーを中心に取引をしています。しかし、ペーパーレス化の流れの中で、お客様のニーズが変わってきました。かつてはプリンター専用機が各社にありましたが、近年では複合機に集約されるケースが増えています。ちなみに、当社が販売しているリサイクルトナーはプリンター専用機のためのものです。複合機はメーカーが純正トナーをカウンター料金制度で提供しているため、当社のリサイクルトナーを販売する余地はありません。
プリンター専用機から複合機への集約など、デジタル化やペーパーレス化の流れの中で需要が変わってきており、それに対応するのがITソリューション事業です。お客様の中には、「プリンターはいらないけど複合機の買い替えをしたい」という方もいらっしゃいます。また、パソコンやセキュリティなど、複合機に付随する様々なニーズにも対応しています。
基本的には顧客基盤は共通で、お客様のサプライとITソリューションの両方を契約いただいているケースも多いです。ITソリューション事業のお客様は中小企業が中心で、従業員50人以下の企業が多いです。情報システム部門を自社で抱えていらっしゃるような大企業は、お客様にはなりにくいです。中小企業の情報システム部門の代行や、情報システム担当者を支援するような形でサービスを提供しています。複合機を起点に、様々な提案やお手伝いをしています。
取材者: なるほど。複合機、プリンター専用機から複合機に変えられるような提案などもされるということでしょうか?
回答者:プリンター用のリサイクルトナーが当社にとって主力の商品ですので、基本的にはそれを守るというスタンスです。しかし、例えば「プリンターはいらないから複合機に統合したい」というお客様に対しては複合機の提案も行えるように、全方位の対応をしています。
取材者:サプライ事業の中で新たに立ち上げたECサイトについて詳しくご説明いただけますでしょうか?
回答者: はい。元々「はっするネット」というECサイトを持っていたのですが、これは受発注システムのようなものでした。Google検索などで外部からお客様が流入してくるようなオープンサイトではなく、既存のお客様にFAXで注文するよりも便利にご利用いただくためのサイトでした。
それを昨年「YORIDORI(ヨリドリ)」というECサイトに一新しました。これはオープンサイトになっており、外部からの集客もできるようになりました。既存のお客様のユーザビリティ向上も図り、外部のお客様と既存のお客様の両方から購買を促進することで、客単価の向上を目指しています。
また、「YORIDORI(ヨリドリ)」はデジタルマーケティングのプラットフォームとしても活用しています。サイトでは様々な商品の紹介だけでなく、ITソリューションに誘導するような記事なども掲載しています。
取材者: デジタルマーケティングを主導できるようになったのは、グループ化したイコリスの影響でしょうか?
回答者: はい、そうです。元々デジタルマーケティングを強化していこうという方向性があった中で、M&Aの話があり、現在はイコリスを中核にケイティケイにもデジタルマーケティングの部署を設け、昨年8月からWebマーケティングを強化しています。
取材者: なるほど。売上高増加要因としてデジタルマーケティングの伸長がありましたが、現状はイコリスの知見を社内に活かして、うまくデジタルマーケティングを回しているということでしょうか?
回答者: 現状、実際に売上利益に直結しているのはイコリスです。決算説明資料などでもITソリューションの中でイコリスのサプリメントや化粧品販売の話に触れておりますが、現時点ではそちらの貢献が大きいです。
外部からの集客など、イコリスの知見を生かして「YORIDORI(ヨリドリ)」を運営しており、サプライ事業の売上にも貢献しつつあります。
取材者:売上増加要因のところで、サプライ事業で新規営業活動に対する取り組みという記載があったかと思いますが、これについてどのような政策や取り組みを行われているか教えていただけますでしょうか?
回答者: はい。これはシンプルに言って、コロナ禍で対面型の営業活動が停滞したため、アフターコロナで改めて営業を強化しているということです。
特に東京では、新規の営業活動が難しくなっていました。当社のリサイクルトナーのメインのお客様は、都心のオフィスだけでなく、製造業、病院、介護、物流などの業界にも多くいらっしゃいます。これらの業界のお客様に対しても、コロナ禍で営業活動が制限されていました。病院などは、なかなか電話やメールでは対応できず、実際に行かないと話ができないところが多いのが現実です。
取材者:サプライ事業に関しまして、サステナブルパートナープログラムについてご説明いただけますでしょうか?
回答者: はい。これは端的に言うと、既存のお客様の囲い込み戦略です。新規顧客獲得も重要ですが、既存顧客の囲い込みも重要です。また、リサイクル業者としての責任を果たすという側面もあります。リサイクルは、トナーカートリッジを回収し、再生して販売するというサイクルを回さなければいけません。しかし、現実には販売したトナーカートリッジを回収できないケースも多いのです。
他の業者に回収されてしまったり、逆に当社が回収する中に売ってないものが含まれていたりするなど、様々な問題があります。そこで、リサイクルカートリッジのトレーサビリティを強化するために、このサステナブルパートナープログラムを導入しました。
具体的には、トナーカートリッジにQRコードを貼っています。お客様がトナーを交換する際に、新しいトナーのQRコードを読み取ってもらうことで、古いトナーが返ってくるということがわかるようになります。そして、それを回収に伺います。お客様のニーズによっては、自動的に発注も行えます。
お客様にとっては、発注や在庫管理の手間が省けます。当社にとっては、QRコードを読み取っていただくことで、回収と同時に次のトナーも自動的に発注いただけることになります。
取材者: なるほど。IoT的な側面があるのですね。
回答者: はい。リサイクルトナーの会社は、ほとんどが販売店を介したビジネスを行っています。当社は数少ない製造直販です。ですので、QRコードで回収や発注ができる仕組みを作れるというメリットがあります。この辺を今後推進していきたいと考えています。
取材者: 確かに直販でなければできないことになりますね。
回答者: はい。
取材者: 貴社はおそらくM&Aなどの戦略もあるかと思いますが、M&Aの戦略として何か、こういう企業をターゲットにしているというのはございますか?
回答者: そうですね。まず、全方位で情報を集めています。サプライ事業においては、例えば同業の文具販売店などで、社長が高齢になり事業承継できず、どこかに事業を譲渡したいというケースが増えています。そのようなケースでは、M&Aというよりも、お客様を引き継ぐというような形になります。少なくとも仲介業者は入らないような、リリースなども出さないM&Aです。
ITソリューション分野では、例えばイコリスのEC事業をどのように広げていくかということを検討しています。ECでBtoCで売りたいけれど、ノウハウがないという会社も多いので、イコリスの知見を活かして何かできないかと考えています。また、全く予想外のデジタル分野のビジネスを持ち込んでくれる方も多く、そのような案件も検討しています。
取材者: 全方位でいろいろ検討されているのですね。
取材者:最後に、貴社の創業の経緯や創業時の思いについてお伺いできますでしょうか?
回答者: はい。創業は1971年で、加藤という者が創業した会社です。当時は「カトー特殊計紙」という社名で、特殊な紙を製造販売していました。この頭文字がKTKという社名の由来です。
その後、Windows95が登場した頃にレーザープリンターが普及し始め、レーザープリンター用トナーのリサイクルビジネスを始めました。その前は、リサイクルリボンを製造していました。これは、銀行のATMで通帳記入する際などに使用されるリボンです。リボンのリサイクルから始まり、今ではインクなどもリサイクルしています。
ケイティケイ単体で2006年にJASDAQに上場しました。その後、文具卸売業の青雲クラウンと株式交換という形で一緒になり、青雲クラウンのオーナー社長である青山がケイティケイの経営も見るようになりました。
取材者: なるほど。ECサイトで文具を幅広く販売できるようになったのは、青雲クラウンの影響もあるのですね。
回答者: はい、そうです。青雲クラウンは歴史のある文具問屋で、商品ラインナップが豊富です。KTKはトナーに特化していたので、文具に関しては青雲クラウンの力を借りることができました。両社にとって大きなシナジー効果がありました。
専務取締役管理本部長兼グループ戦略本部長 葛西裕之様
―
